新刊案内/トピックス
-
渥美半島 四季ものがたり
-
追想 渥美半島の昭和ーふるさとへの想いは遥か永遠にー
-
上海東亜同文書院大学図書館の世界―その激動の軌跡から解き明かす―
-
豊田珍彦『豊橋地方空襲日誌』を読む
-
崋山渡邉登
-
ふるさと「私」の始原
-
豊橋と陸軍師団-歴史と建物
-
渥美半島の戦後 -失われつつある記憶を次世代に繋ぐ-
-
正徳・享保期の三河吉田藩 松平信祝とその時代
-
磯丸様のまじない歌
-
輝いていた時代の 中田島砂丘 出雲崎漁村
-
渥美半島の昭和 -57編の手記から甦る30年代-
-
笑いの健康学 TEXT BOOK
-
東三河の古墳 1,600基の古墳はどうして築かれたのか
-
渥美半島 太平洋岸の海岸線を追う ー表浜海岸の侵食を見直すことからー
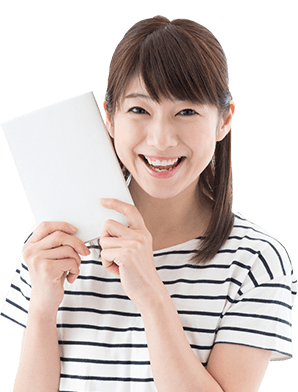
自費出版をお考えの方
自費出版をお考えの方
お客様のご希望とご予算をうかがった上で最も合った作り方を一緒に考え、ご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。
- 自分史
小説
エッセイ
旅行記
詩集
句集 - 短歌集
専門書
絵本
写真集
画集
コミック - 記念誌
遺稿集
社史
学校・大学教材
研究所
論文 など
お問い合わせ
 〒442-0821愛知県豊川市当古町西新井23番地の3
〒442-0821愛知県豊川市当古町西新井23番地の3
株式会社シンプリ内
| 電 話 | 0533-75-6301 | ファックス | 0533-75-6302 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| メール | info@sinpri.co.jp お問い合わせフォーム | ||||
 〒442-0821愛知県豊川市当古町西新井23番地の3
〒442-0821愛知県豊川市当古町西新井23番地の3株式会社シンプリ内